おひとりさまという言葉

「おひとりさま」の“さま”は、私自身への愛とリスペクトだ。
それは寂しい独りぼっちの孤独ではなく、唯一の一人である私自身と親友であるための哲学だと思っている。
誰かと一緒にいることで生まれる妥協や我慢から、そっと距離を置いて、自分の本音に耳を澄ませるための選択。
「ひとりでいること」は、孤独ではない。
それは、自分の人生を自分で選び、自分で育てていくための、静かで力強い哲学だ。
「一人であり一人ではなく、一人ではないけど一人である」
私は自分の人生を生きるとはこういう事なのだろうと思っている。
一見すると矛盾しているように感じるけれど、この世に生きている限り、現実的に人間のつながりはどこかに必ず存在する。学校にも、会社にも、家庭にも、さっきコーヒーを買ったカフェにも、そしてこうやってインターネットの中にも。
しかし、精神は私という魂そのもの、唯一の存在で、自分の道は自分にしか選ぶことができないし進むことができない。
- 「一人である」とは、他人に依存せず、自分の喜びや責任を自分で引き受けること。
- 「一人ではない」とは、友人や家族、自然や社会とのつながりを感じながら生きていること。
- 「一人ではないけど一人である」とは、つながりを持ちながらも、最終的には自分自身と向き合い、自分の人生を主体的に生きること。
この言葉は、私自身が長年の経験を通してたどり着いた生き方の哲学です。
孤独を恐れず、でも人との関わりを大切にし、すべてを自分の責任として受け入れる——
それが、私にとっての「おひとりさま」の本質なのです。
今回は、私がこれまでの人生の中で向き合い続けてきた「ひとり」という存在について、そして今実感している「おひとりさま」という言葉に込めた私なりの哲学を綴ってみたいと思う。
誰とも違う、私の感覚

今から7年ほど前のこと。私は長野県最北端の村の、さらに山奥の秘境に単身で移住した。
そして現在はその山奥暮らしから離れ、実家のある愛知県に戻り、介護職として普通に勤め人をしている。
先日、「おひとりさまを楽しむようになったきっかけ」の記事を書いていて、あの頃の山奥暮らしを振り返っていたとき、ふとこの言葉が浮かんだ。
一人であり一人ではなく、一人ではないけど一人である
私は子どものころから一人だった。そう思っている。
とはいえ、両親と姉と住んでいたし、友達もそれなりにいた。いじめられていたわけでもない。
だけどどこか、いつも誰とも気が合わない気がしていた。
その感覚は20歳になるまで変わらなかった。
友達を親友だと思ったことが一度もなかったのだ。
小学生の時も中学生の時も高校生の時も、同じものを見たり聞いたりして同じように楽しいとはしゃいだり夢中になったり、なんでも心の底から話せると思った友達は居なかった。
どこか「私とは違う」と冷めた視点があったことは覚えている。
心が通った、たった一人の人
20歳の時、バイトで知り合った2歳年上の女の子のことを、初めて親友だと思った。
彼女はとてもさっぱりとした性格で、お世辞を言ったり嘘を言ったりしないと感じた。
媚びないのに周りとの付き合い方が上手で、男女問わず友達の多い人だった。
そのうえファッションや音楽のセンスも抜群に良くて、私ととてもよく付き合ってくれた。
生まれて初めて親友だと思った人だし、そう思うのはあとにも先にも彼女だけだった。
今思えば、彼女は私にとって憧れで尊敬の対象だったのだと思う。
彼女にとって私が親友だったかどうかはわからないし、もっと親しい間柄の人はいたと思うが、私は嫉妬心みたいなものも感じたことがないくらい、彼女のことが大好きだったし、何よりもリスペクトしていたのだ。
おそらく、人に対して心を開いたのは彼女が初めてだったと思う。
いつもどこにいても浮いていて、分かり合える人なんていないと冷めていた自分にとって、
共感してくれたり、信じてくれたり、否定しないでいてくれる人が存在するのだという事を
彼女と出会って初めて知ったのではないかと思う。
彼女に出会わなければ、私は一生自分を肯定できなかったかもしれない。
自分だけの人生があるということもわからないままだったかもしれないと
いま、こうやって振り返ってみて改めて気付いた。
もう十年以上連絡していないけど、またいつか彼女に会ってお礼が言いたいと思った。
居場所を探していた日々

彼女と過ごしたあの楽しい学生生活から、あっという間に10年が経った。
その後どこへ行っても居心地が悪く、私は転職を繰り返しながらその度に、社会と人間関係に絶望し、何者にもなれずに実家でくすぶっていた。
ずっと自分の場所を探していたし、友達なりパートナーなりの自分の相棒を探していたけれど、しっくりくる場所にも相棒にも出会えないままだった。
そんな何となく満たされない日々を過ごしていたが、猛烈に自分を変えたいという衝動にかられ、
なぜか山登りをしたいと思い立った。
アウトドアファッションが好きだったことが発端だが、ファッションだけアウトドアというのは何とも中身がなくてかっこ悪いと思ったのだ。
さしずめ丘サーファーならぬ町ハイカーというところ。
自然はもともと好きだったが、山というところは一人では入ってはいけない危険な場所という認識があったし、何か現状と自分を変えたいという思いと、ならばついでに出会いも求めつつという下心込みで、社会人山岳会に勇気を出して入会した。
山と人との間で

山岳会に入会し、毎月の会合、そして飲み会。
毎週のようにパーティーを組んで山に登り、新しい会員も増えていき、怒涛のように人間関係が出来上がっていったし、恋もした。
そんな日々があっという間に2年過ぎた。気づくと私は山が大好きになっていた。
その一方で、私はこの場所で一生ものの関係が築けるかもしれないという期待も抱いていた。
誰かと深くつながりたい、認められたい、人気者でいたい——そんな欲や邪念のようなものも、正直なところあったと思う。
でも、そうした思いはいつしか疲れにもつながっていって、恋愛も成就せず。
特に、年上の先輩会員との縦の関係の中で配下として振る舞うことに、次第に息苦しさを感じるようになっていた。
山の中では自由でいられるのに、人間関係の中では私らしさを見失っていて、どこか窮屈だった。
自然との対話が始まった

登山経験を重ねるうちに、私の山に対する知識やスキルも上がり、参加する登山が本格化していった中で、周りの仲間との「山に入る目的」の根本的な違いも感じるようになった。
会員の多くは、山頂を制覇すること、難易度の高いルートを攻略することを目的としていた。
私の中にも、それに対する興味がなかったわけではないけれど、私の感じる山とは、ちょっと違うのではないかと思うようになったのだ。
登山道が整備されているとはいえ、山の中というのは、やはり人間の世界ではない。
そこは、鳥のさえずり、ときにわななきが聞こえ、虫の羽音が耳元で震え、獣の匂いが漂う場所。
姿は見せずとも、彼らは確かに山の中に生きている。
街では傘を差せばしのげる雨も、山の中では瞬く間に体温を奪っていく。
雷はいつ人間の体を貫くやもしれず、太陽はその冷えた体を温めてくれることもあれば、容赦なく煮やしてしまうこともある。
登山をするようになって、私は自然というものに対して、強く畏敬の念を抱くようになった。
孤独と強さのあいだで

アルプスに登頂したとき、森林限界を超えた山の上で体に浴びた太陽の光は、街に注ぐ優しい光とはまったく違うものだった。
それは、地球すべての命を制する光であり熱なのだと、肌で感じた。
そのとき、その思いを語れる相手は山岳会の中に誰かいただろうか。
私は山岳会の中で、無邪気な自分を演じながら、一人心の中でその思いをかみしめていたように覚えている。
それから、私は一人で山に入るようになった。
一人で入る山は、心細く、パーティーで登っていたとき以上に山への怖さを感じた。
けれどその怖さは、私にとって大切なものだった。
慎重に、自分をおごることなく、山と向き合い続けた。
自ら挑みながらも、「なぜこんな苦しいことをしているのか」と分からなくなり、泣きながら山を下った日もあった。
それでも、山に入ることをやめなかった。
一つ山に入るごとに、「私は出来るんだ」と自信も一つ増えていった。
そして、いつしか——
揺るぎない強さが、私の中に静かに育っていった。
森と人とのつながりを学ぶ

山とは一体何なのか。自然のこと、森や木のことをもっとちゃんと知りたい——
山と向き合う中でそんな思いが芽生えた頃、市が主催する「森林学校」という講座の存在を知った。
早速その講座に参加することにした。
講座の中では、森林の植生を知り、木が私たちの暮らしの中でどのような影響を持っているのか、そして植物同士や虫・鳥・動物との共生関係などを学んだ。
私たち人間が地球上で社会を構築しているのと同じように、自然界でも野生の動植物たちが相互に関係しあって社会をつくっているのだと知ったとき、今まで以上に山や森林に対して神秘的な魅力を感じた。
そして、私たち人間はこの自然の一部として、動物の一部として、どう関わりながら生きていけばいいのか——
そんなことを考えるようになった。
共に学び、暮らしを見つめ直す

その後、これもまた市が主催する「なりわい塾」という講座に出会う。
一年にわたるこの講座の中で、「人と自然」「人と人」、そして地域とは何か、共生とは何か——
そんなことについて仲間たちと学んでいくこととなった。
この学びと出会いは、私の「ひとり」のあり方をさらに深めてくれた。
次回は、なりわい塾での経験から山奥暮らしへ、そして今の「おひとりさま」という価値観に至るまでの道のりを辿ってみたいと思う。
続く
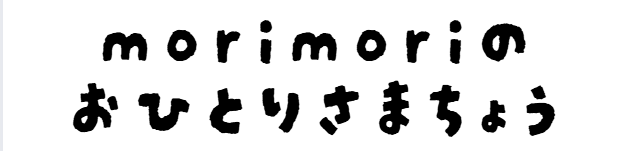

コメント